
化学メーカーの半導体材料動向について調査しました!
調査日:2025/02/22
導入
日本の化学メーカーは、半導体産業の材料供給において不可欠な存在です。シリコンウェーハやフォトレジストなど、多くの重要材料で日本企業が高い世界シェアを握っており、世界の半導体サプライチェーンを支えています。例えば、フォトレジスト(感光材)では日本勢が世界供給の約8割を占め、最先端品でもJSRや東京応化工業、信越化学工業といった企業が主導的地位を維持しています。またシリコンウェーハでは信越化学工業とSUMCOの2社で世界シェアの約57%を占めるなど、素材分野で圧倒的な競争力を発揮しています。
本記事では「日本の化学メーカー」による「半導体材料動向」を世界市場の観点から詳しく分析します。2023年から2025年にかけての最新技術動向や市場規模、競争環境を整理し、日本企業の強みと課題、そして今後の展望を考察します。半導体材料分野の最新情報を把握することで、日本企業の競争力や市場ポジションについて理解を深めることができるでしょう。
日本の化学メーカーと半導体材料の概要
日本には半導体材料で世界をリードする主要化学メーカーが多数存在します。それぞれの企業は独自の強みを持ち、多様な材料を供給しています。主な企業と特徴は以下の通りです:
- JSR株式会社(ジェイエスアール):1957年創業。半導体用フォトレジストで世界トップシェアを持ち、EUVレジストなど先端材料の開発を牽引しています。2023年には日本政府系ファンドによる買収提案を受け入れ、国家戦略物資として位置付けられました。
- 東京応化工業株式会社(TOK):国産初のフォトレジスト開発企業。フォトレジストと関連薬液(現像液など)で世界的地位を確立し、EUV対応製品も展開中です。
- 信越化学工業株式会社:世界最大のシリコンウェーハメーカーで、300mmウェーハなどで世界シェアトップ(約30%)。フォトレジスト事業も手掛け、高純度化学薬品など幅広い材料を提供しています。
- 住友化学株式会社:総合化学メーカー。半導体向けには ArFエキシマ用レジストや化学材料を展開。近年は液晶材料事業を縮小し半導体材料分野を強化する戦略をとっています。
- 富士フイルム株式会社:写真フィルム技術を応用し、半導体用のフォトレジストやCMPスラリー、洗浄剤などプロセス薬品を提供。近年は国内にCMPスラリー工場を新設するなど積極投資しています。
- 株式会社レゾナック:大手の昭和電工と日立化成が合併して誕生しました。日立化成はCMP研磨材や実装材料で強みを持ち、昭和電工はエッチングガス(フッ素系ガス)やスパッタリングターゲット材などを供給していたことから、半導体材料を幅広く網羅しています。
- 三菱ケミカルグループ(旧三菱化学・三菱ガス化学など):フォトマスク基板用の石英ガラスや高純度ガス、配線用樹脂材料などを手掛ける大手です。総合力で材料ソリューションを提供しています。
- その他の企業:シリコンウェーハではSUMCO株式会社(住友と三菱の共同出資で設立)が信越化学に次ぐ大手です。高純度薬液では関東化学やステラケミファが、フォトマスク用ブランクスではHOYAや東京応化工業が高シェアを持ちます。パッケージ基板用樹脂フィルムでは味の素株式会社の開発したABF(Ajinomoto Build-up Film)が事実上の標準素材になるなど、異業種企業も重要な役割を担っています。
半導体材料の種類と製造プロセスにおける重要性
半導体チップ製造では、さまざまな化学材料が各工程で使われます。主な材料とその役割は以下の通りです:
- フォトレジスト(感光材):リソグラフィ工程でシリコンウェーハ上に回路パターンを描くための感光性樹脂です。紫外線やEUV光を照射すると化学反応を起こし、不要部分を溶解除去することで微細パターンを形成します。最先端チップ製造には高感度・高解像度のフォトレジストが不可欠で、日本企業がEUV対応品をリードしています。
- CMPスラリー:CMP(化学機械研磨)工程で用いられる研磨液です。酸化物膜やメタル配線層を平坦化するため、シリカやアルミナなどの微粒子(砥粒)と化学薬品を混ぜたスラリーを用いて表面を研磨します。CMPスラリーの品質はデバイスの平坦度や良品率に直結するため、高度な分散技術と安定供給が求められます。
- エッチングガス(反応性ガス):ドライエッチング工程で用いられる高純度ガスです。例えばシリコンやシリコン酸化膜の選択的エッチングにはフッ素系ガス(CF₄、SF₆など)が使われ、液体材料のエッチングには気体のフッ化水素(HF)なども用いられます。日本企業は高純度フッ化水素の供給で世界をリードしており、その供給網は先端半導体の量産を支えています。
- 高純度化学品(超純水・洗浄液・現像液など):半導体製造では不純物を極限まで排除した化学薬品が必要です。たとえばシリコンウェーハ洗浄用の超純水や硫酸・アンモニア水溶液、フォトレジスト用現像液(TMAH液)などがあります。日本の高純度薬品メーカーは60年以上にわたる精製技術の蓄積があり、微量不純物まで管理された製品を提供しています。
- その他の材料:シリコン単結晶ウェーハは半導体の土台となる基板素材で、日本勢(信越化学、SUMCO)が世界市場を席巻しています。配線材料としては高純度の銅やアルミニウム、絶縁膜用の有機低誘電率材料、パッケージ用樹脂やはんだ材料など、多岐にわたる材料が使用されています。フォトマスク原板やEUV用マスクブランクスではHOYAなど日本企業が高シェアを持ち、露光用のフォトマスク保護膜(ペリクル)用フィルムも開発が進められています。
このように、日本の化学メーカーは半導体製造プロセスのあらゆる段階で必要となる材料を供給し、それぞれの分野で高い品質とシェアを有しています。その強みは世界の半導体産業を下支えする重要な要素となっています。
主要企業の最新動向・研究開発の事例
近年(2023~2024年)における日本の主要化学メーカー各社の動向や研究開発の例をいくつか紹介します。材料技術の革新や供給体制強化のための投資が相次いでおり、業界再編も含め活発な動きが見られます。
JSR株式会社の動向
2023年6月、JSRは日本政府バックの投資ファンドである日本投資法人(JIC)による約9039億円の買収提案を受け入れ、株式非公開化(プライベート化)に合意しました。JSRは先端フォトレジストの世界最大手であり、米中対立下で半導体材料サプライチェーン強化が国家課題となる中、日本政府が直接支援に乗り出した形です。JSR自身もEUVレジストの開発や量産に注力しており、ベルギーのimecや米インテルとの協業を経てEUV対応材料を実用化しています。また、韓国やアメリカなど海外現地拠点での生産能力増強にも取り組み、グローバルな供給体制を整備中です。
信越化学工業の動向
信越化学は半導体材料で盤石な地位を維持しつつ、新規投資にも動いています。報道によれば、2024年に群馬県伊勢崎市に約830億円を投じて半導体フォトレジストなどの新工場建設を計画しており、国内で56年ぶりの新生産拠点となる見通しです。この工場は2026年稼働予定で、製造したレジストを韓国・米国など世界に輸出する戦略拠点となります。信越化学は現在、世界のフォトレジスト市場で約20%のシェアを持ち、EUVやArFといった先端製品分野ではシェア40%超を目指すとされています。またシリコンウェーハ需要増に対応し、新潟や台湾の工場でも増産投資を継続しています。
住友化学の動向
住友化学は2024年に入り、液晶パネル向け部材から半導体材料への事業シフトを鮮明にしています。台湾報道によると、同社はLCD材料部門を縮小する一方で、フォトレジストや先端半導体化学品への投資を加速させています。具体的な例として、EUV時代を見据えた新規材料開発や他社との提携強化が挙げられます。住友化学はArFエキシマレジスト技術で実績があり、近年はEUV用樹脂材料でも研究開発を進めています。また子会社を通じ、シリコンカーバイド(SiC)などパワー半導体材料分野にも参入し、新成長分野の開拓を図っています。
富士フイルムの動向
富士フイルムは半導体プロセス材料事業を成長ドライバーの一つに位置付け、積極的な設備投資を行っています。2022年には熊本県に約20億円を投じ、同社として日本初となるCMPスラリー(研磨液)の生産拠点を開設しました。この工場は2023年に本格稼働し、需要増に応えるため世界4拠点目のCMPスラリー供給基地となっています。CMPスラリー市場は年10%成長と見込まれており、富士フイルムは台湾TSMCなど主要顧客への安定供給を強化しています。また、2025年春には同じ熊本拠点でイメージセンサー用のカラーフィルター材料製造設備も稼働予定で、製品ラインナップ拡充による電子材料事業の売上高2030年5,000億円目標に向け動いています。
三井化学の動向
三井化学は半導体用フォトマスク保護フィルム(ペリクル)分野で投資を行っています。山口県岩国市の工場に数十億円規模を投じて新ラインを増設し、2025~2026年に量産開始予定です。ペリクルは露光用マスクを塵埃から守る薄膜で、EUV露光では高い技術ハードルがありますが、同社は高透明度・高強度の膜材料開発に注力しています。これにより国内外の露光装置メーカーやデバイスメーカーに対し、高品質なペリクルを供給し国産化率向上に貢献する計画です。
ガス・高純度薬品メーカーの動向
産業ガス大手の日本酸素ホールディングス(旧大陽日酸)は、2026年頃までにネオンガスの国内生産を開始する計画です。ネオンは露光用エキシマレーザーガスの原料として不可欠ですが、ウクライナ情勢の影響で供給リスクが指摘されました。同社は安定供給のためロシア以外からの原料調達や国内精製設備の導入を進めています。また高純度薬液では関東化学が2023年に茨城県で新工場を稼働させるなど、生産能力増強とBCP対応を図る動きがあります。
新規プレイヤー・技術革新の事例
異業種から半導体材料への参入も進んでいます。大阪有機化学工業株式会社は高度精密化学で知られますが、Argon Fluoride (ArF)レジスト用モノマーで世界市場シェア70%を占める隠れたキープレイヤーです。同社はEUVレジスト向け材料でもシェア拡大を狙い、最先端材料市場で存在感を高めています。また製紙大手の王子ホールディングスは木材由来のバイオマス資源からフォトレジストを開発するプロジェクトを進めており、2028年頃の実用化を目指すと報じられています。木質資源から環境負荷の低いレジストを製造する試みで、次世代2nmプロセス以降の需要に応える狙いがあります。こうした新規参入や技術革新は、日本の材料産業に新たな競争力と選択肢をもたらそうとしています。
半導体材料市場の規模と予測(2023年~2025年)
世界の半導体材料市場は近年拡大を続け、2022年に過去最高の売上高を記録しました。しかし2023年は半導体市況の調整局面となり、材料需要も一時的に減速しています。SEMI(国際半導体製造装置材料協会)の統計によれば、2022年の世界半導体材料市場規模は727億ドル(過去最高)で、2023年は前年比8.2%減の667億ドルへ縮小しました。これはメモリ市況の低迷による在庫調整やファブ稼働率低下が影響したためです。
しかし2024年以降は需要が持ち直し、再び成長軌道に乗る見通しです。トレンドフォースの分析では、2023年後半から在庫調整が進み、AI需要や車載半導体の拡大も相まって半導体市場は2024年に回復に向かうとされています。半導体材料市場も2024年には2022年のピーク水準を回復し、その後も緩やかな成長が予測されています。特に先端プロセス向け材料(EUVレジストや高性能基板など)は需要の牽引役となり、高成長が期待されます。
日本企業の世界市場シェアに目を向けると、半導体材料全体では日本勢が依然大きな存在感を示しています。調査会社Omdiaのデータによれば、2022年時点で日本企業は半導体材料分野で世界シェア48%を占めています(金額ベース、シリコンウェーハやフォトレジスト等を含む)。中でもシリコンウェーハでは約56%(信越化学・SUMCO)、フォトレジストでは50~80%程度(製品範囲による、JSR・TOK・信越化学など)、フォトマスクブランクスではHOYAが約80%、ABF樹脂では味の素がほぼ100%、高純度フッ化水素やポリイミド樹脂でも日本の数社が寡占的地位にあります。このように多数の重要材料で日本メーカーが高い競争力を持っており、グローバル市場における日本企業の存在感は依然として強みとなっています。
今後2025年にかけての市場予測としては、半導体需要の拡大に伴い材料市場も拡大が見込まれます。AI向け先端ロジックや電気自動車向けパワー半導体の伸長が材料需要を押し上げ、2025年の世界材料市場規模は再び700億ドル台半ば~後半に達すると予測する機関もあります(年率5~10%成長)。日本企業もこの需要増を取り込みつつ、高付加価値品へのシフトや生産能力増強で売上成長が期待されます。一方で、為替変動や地政学リスク、中国など新興国企業の台頭によるシェア変動には引き続き注意が必要です。
技術トレンドと課題
半導体材料分野では、技術革新の加速とともに日本の化学メーカーが直面する新たなトレンドと課題がいくつか存在します。ここでは主要なトレンドと課題を挙げます。
EUVリソグラフィと先端プロセス対応
7nm以下の先端ノードではEUV(極端紫外線)リソグラフィが本格導入され、対応する材料技術が要求されています。日本企業はEUV用フォトレジストや高NA対応の新材料開発に注力しており、JSRや東京応化工業は海外の研究機関と連携して次世代レジストを開発中です。EUVレジスト市場は2025年までに全フォトレジスト市場の10%に達すると予想され、今後も大きな成長ポテンシャルがあります。一方でEUV向け材料は感度と線幅制御の両立が難しく、新素材の探索やナノ粒子の利用など技術課題も残っています。日本メーカー各社は最先端プロセスに適応すべく、研究開発投資を拡充し競争力強化を図っています。
供給安定性と経済安全保障
半導体材料の安定供給は各国にとって戦略的に重要となっています。2019年には日本が韓国向けフォトレジストや高純度フッ化水素の輸出管理を厳格化し、韓国の半導体生産に影響が及ぶ事態がありました。これを契機に韓国では材料国産化が進み、Dongjin SemichemやSKマテリアルズがArF・EUVレジストの国産化に成功するなど一定の成果を上げています。中国でも中低端品で国産化率30%に達し、ArF/EUVレジストの開発を加速させています。日本企業にとっては地政学リスクへの対応と、信頼性の高いサプライチェーン維持が課題です。そのため、国内外に分散した生産拠点の確保や在庫備蓄、政府との連携による輸出規制対応など、経済安全保障の観点からの戦略が求められています。
コスト競争力と収益性
半導体材料は高付加価値製品ですが、競合激化により価格競争も起きています。日本企業は品質面で優位性がある一方、人件費やエネルギーコストの高さから収益圧迫の懸念があります。また、材料需要の変動(シリコンサイクル)により業績が左右されやすい面もあります。今後、中国企業など低コスト競合の台頭も予想され、日本メーカーは高機能化と生産効率向上でコスト競争力を維持する必要があります。例えば製造プロセスの自動化・省エネ化、新触媒の導入による歩留まり改善などが進められています。
環境対応(SDGs・グリーンケミストリー)
世界的な環境規制強化の中で、半導体材料メーカーにも持続可能性への対応が求められます。製造時の温室効果ガス排出削減や、使用後の薬品廃液処理、高GWP(温暖化係数)ガスの代替開発などが課題です。欧州ではPFAS(フッ素系化合物)規制案が議論されており、フッ素系フォトレジストやコーティング材料への影響が懸念されています。日本企業各社はグリーンケミストリーの観点から、バイオマス由来材料への転換やプロセス改善に取り組み始めています。前述の王子HDによる木材由来フォトレジスト開発もその一例で、環境負荷低減と技術革新を両立する試みです。また、製造プロセスで排出される副生成物の回収・再利用や、省資源型の製造装置開発(例:現像液の循環利用システム)など、SDGsに沿った取り組みが産官学で進められています。
競争環境と海外メーカーとの比較
半導体材料産業の競争環境はグローバル規模で展開されており、日本企業は各分野で海外メーカーとしのぎを削っています。主要材料ごとに日本勢と海外勢の状況を比較します。
フォトレジスト分野
日本企業(JSR、TOK、信越化学など)は高いシェアと技術力を持ち、特にEUVやArF先端品では圧倒的優位にあります。一方、海外では米国のデュポン(旧ダウ・ケミカル系)やドイツのメルク(旧AZエレクトロニクス)も主要プレイヤーです。また韓国・中国の新興企業が政府支援の下で技術開発を進めており、中長期的に競争が激化する可能性があります。
CMPスラリー・研磨材分野
日本からは富士フイルムやフジミ工研、レゾナックなどが参入し、高品質な製品で評価を得ています。海外勢では米エンテグリス(Entegris、旧キャボットマイクロエレクトロニクス)や独メルク(ヴァーサム買収)、化学大手のBASFなどが競合し、市場は数社による寡占状態です。トッププレイヤーの寡占率は50%以上とされ、各社が顧客ニーズに合わせたスラリー配合技術を競っています。
エッチングガス・高純度ガス分野
日本酸素ホールディングス(大陽日酸)は日本唯一の大手半導体ガスメーカーで、エッチング用フッ素ガスやレーザーガスで実績があります。グローバルではフランスのエア・リキード、ドイツのリンデ、米国のエアプロダクツといった産業ガス大手が世界市場をリードしています。韓国SKマテリアルズもNF₃(窒化フッ素)などで世界トップシェアを持ち、韓国勢も存在感を示します。日本企業は超高純度化や安定供給で強みを出しつつも、市場規模の大きい汎用ガスでは海外勢との競争が続いています。
シリコンウェーハ分野
トップの信越化学とSUMCOで世界シェア過半を占め、日本がこの分野を席巻しています。競合はドイツのシルトロニック(Siltronic)と台湾のグローバルウェーファーズが続き、韓国SKシルトロンが追随する構図です。300mmウェーハは日本勢がリードしていますが、中国が国産化を図っており、大口径ウェーハの新規参入も注視されています。
パッケージ材料分野
高密度パッケージ基板用のABF樹脂では味の素株式会社が開発したABFフィルムが事実上の標準となり、個別製品レベルでは独占的地位を築いています。基板そのものの製造では台湾や中国のPCBメーカーが台頭していますが、日本企業も絶縁膜材料や封止樹脂などニッチ領域で存在感を示します。またフォトマスク用ブランクス(原板ガラス)ではHOYAとAGCが世界シェアの大部分を占め、EUVマスクブランクスでもHOYAが約8割を供給するなど、日本勢が不可欠なポジションを維持しています。
総じて、日本の化学メーカーは多くの材料分野で高シェア・高品質を実現し競争優位にあります。しかし、一部分野では米欧の化学大手(デュポン、メルク、BASF等)とのシェア競合があり、新興国企業のキャッチアップも進行中です。各社は研究開発力と信頼性で先行する一方、海外メーカーは大型買収や政府支援を背景にポートフォリオ強化を図っており、今後もグローバルな視点での競争戦略が求められます。
今後の展望と成長戦略
日本の化学メーカー各社と政府・大学など産官学は、半導体材料分野での将来展望に向けて様々な成長戦略を描いています。以下、今後の注目動向と戦略をまとめます。
産官学連携と政府の支援策
先端半導体を国家戦略と位置付ける日本政府は、製造プロセスのみならず材料分野への支援も強化しています。JSRの経営権取得に見られるように、重要材料企業への出資・支援や、研究開発補助金の供与など政策的後押しが行われています。また、官民協働の研究拠点整備も進んでおり、ベルギーのimecや米IBMと連携した先端プロセス研究、国内では株式会社Rapidusの設立とともに材料開発のための評価環境整備が検討されています。NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプロジェクト採択を受けてバイオマス製造技術コンソーシアム(王子HDやJGC等参加)が発足するなど、新材料創出のための産官学ネットワークも形成されています。政府の後押しは、日本企業がリスクの高い先端開発に挑戦する支えとなり、海外勢との競争に打ち勝つ基盤となるでしょう。
新規参入・異業種企業との協業
前述の王子HDの例のように、異業種から半導体材料への参入が増えています。素材・化学の基盤技術を持つ企業が自社強みを活かし、半導体向けに応用開発するケースです。紙パルプ、石油化学、医薬品など他分野の企業との協業も加速しています。例えば製薬企業の精密合成技術をレジスト材料合成に活かしたり、自動車部材メーカーがパワー半導体用封止材に参入する動きもあります。日本の強みである多様な素材産業の知見を融合することで、革新的な材料創出やコストダウンを実現しようという戦略です。オープンイノベーションやベンチャー投資も活発化しており、スタートアップ企業との連携による高速な技術開発も期待されています。
グローバル展開とサプライチェーン戦略
日本企業は国内拠点の強化のみならず、グローバル展開にも力を入れています。主要顧客である海外半導体メーカーの近隣に生産拠点を設ける動きが典型です。例えばTSMCが熊本に新工場を建設するのに合わせ、東京応化工業(フォトレジスト)やSUMCO(ウェーハ)、水処理化学のOrganoなど多数の材料サプライヤーが九州に集積しつつあります。この「サプライヤー集積」は物流コスト削減や緊急時対応に有利であり、地域クラスターとしての競争力を生みます。また、日本企業は北米・欧州・アジア各地に生産や開発拠点を展開し、現地調達ニーズに応えています。現地法人を通じたきめ細かな技術サポートや共同開発も行い、グローバル顧客との関係強化を図っています。サプライチェーン全体の最適化とリスク分散を意識した戦略が今後さらに重要になるでしょう。
技術革新と人材育成
材料技術の革新サイクルはますます短期化しています。日本企業が今後も優位を保つには、EUV後の次世代リソグラフィ(例:ナノインプリントやマスクレス露光)への対応、新材料(2D材料やカーボンナノチューブなど)の実用化、高速・低消費電力デバイス向けの材料開発など、先を見据えた研究開発が欠かせません。各社は大学や研究機関との共同研究講座を設置し、基礎研究から製品化まで一貫したイノベーション体制を整備しています。同時に、人材育成も喫緊の課題です。高度な化学・材料工学の知識を持つ若手技術者の育成や、海外人材の登用が進められています。半導体材料はニッチな専門領域が多いため、社内での職人技術の継承と標準化も重要です。これらを推進することで、日本の化学メーカーは長期的な競争力を維持し、新たな市場機会を捉えることができるでしょう。
おわりに
日本の化学メーカーによる半導体材料の最新動向を世界市場の視点で見てきました。日本企業はフォトレジストやシリコンウェーハをはじめ数多くの材料で世界トップクラスのシェアと技術力を持ち、半導体産業の発展に大きく貢献しています。市場規模は一時的な調整局面を経ながらも中長期では拡大が続き、先端技術の進展に伴い新たな材料ニーズも生まれています。日本勢にとっては、その強みを活かしつつグローバル競争に対応し、技術革新と供給体制の強化を図ることが成長の鍵となります。
これから2025年にかけて、「最新技術」への追随や「競争環境」の変化に直面しますが、日本の化学メーカーには長年培った材料開発力と品質への信頼があります。政府の後押しや産官学連携も追い風に、世界の半導体材料市場で日本企業が引き続き重要な役割を果たすことが期待されます。引き続き市場動向を注視しつつ、日本発のイノベーションが半導体産業全体を前進させることに注目が集まっています。
参考文献
- Japantimes, “Japan unveils ¥904 billion deal to buy out chip linchpin JSR”
- TrendForce, “Analysis of the Global Photoresist Market in 2023”
- Fujifilm プレスリリース, 2022年12月15日「熊本拠点におけるCMPスラリー新工場の本格稼働開始」
- Semiconductor Digest/SEMI, “2023 Global Semiconductor Materials Market Revenue Declines…”
- TSMCの日本拠点強化と日台産業協力がカギに | 武者リサーチ
- SemiEngineering, “Mixed Outlook For Silicon Wafer Biz”
- Digitimes Asia, 「Sumitomo Chemical downsizes LCD materials, scales up investment in semiconductor materials」
- Reuters (via MarketScreener), “Japanese chemicals company sees potential niche in EUV chip making materials”
- Digitimes Asia, 「Japan-based semiconductor material suppliers cluster in Kyushu thanks to TSMC」
- Brookings, “The renaissance of the Japanese semiconductor industry” (日本企業の材料・装置シェア)
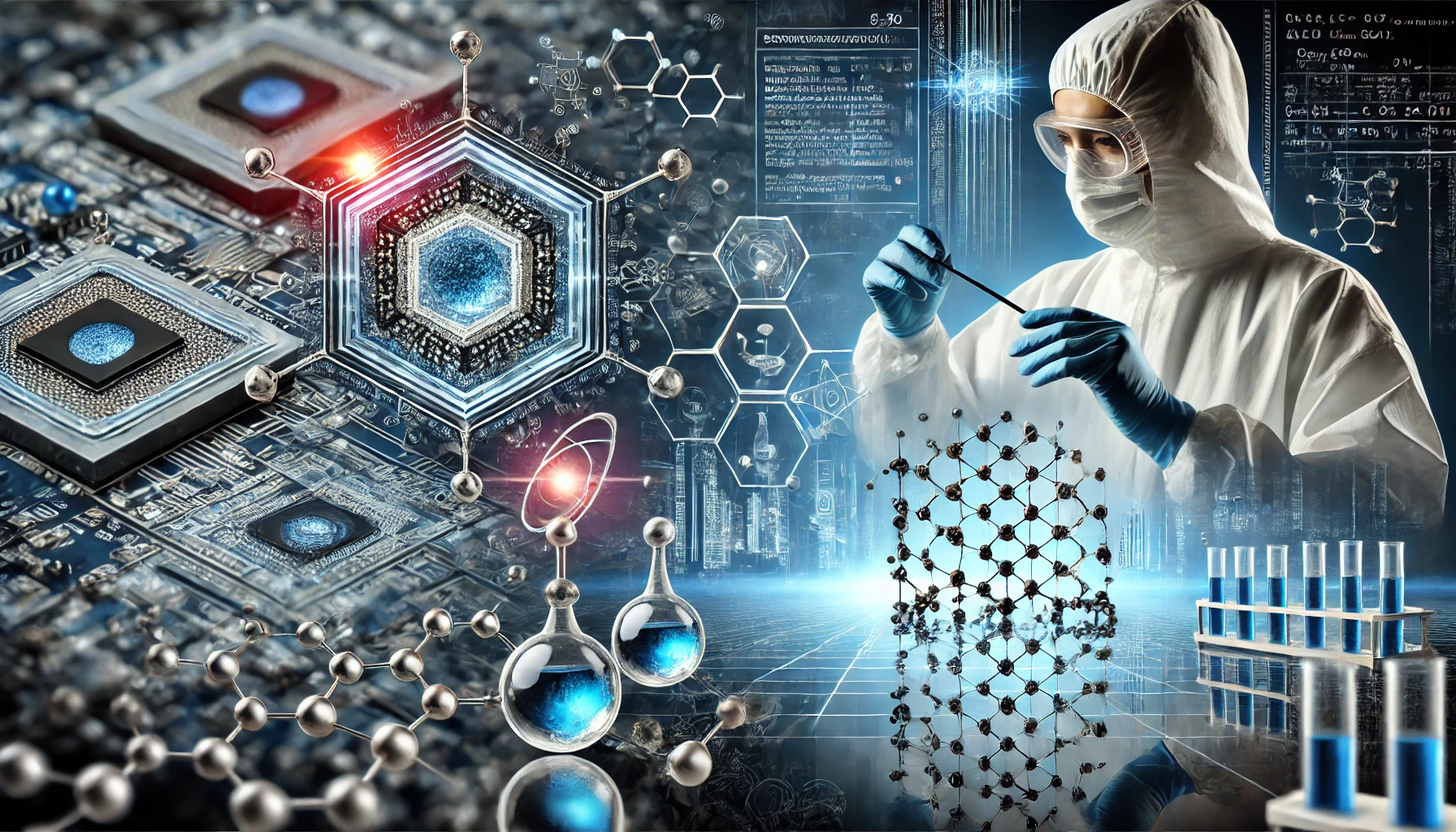


コメント